自然の中ではぐくむ ~こどもたちの心と体~
*「開発途上国」と呼ばれるこどもたちの、哲学者のような表情。
1つのことをやり続け日々生きている
*道具を開発する=人間の能力低下
*最近の5歳児の運動能力=35年ほど前の3歳児と同程度(注1)
*戦後体格は良くなっているが、運動能力は下がり続けている
*AIなど技術が生活全般に。自宅で仕事、教育。
→コミュニケーション力が育まれなくなる
*「発達障害」と診断名を付けられるこども達が増えている
→「増えている」のは環境の問題
*食・環境・生活… 「身体の問題が抜けている」
教育者や親が考えられていない
*公園=すべり台、ブランコ、砂場。
「これで遊びなさい」と大人が間接的に管理している。
こどもの自主性・能動性を奪っている
※プレイパーク増設の重要性
*適応してしまう=心のどこかに欲求不満を抱える
→いじめが起こる
*戦後の日本は「生きる目標」が見えていた。
現代は経済も、がんばってもがんばっても見えない。
=日本人は「生きる目標」を見つけられていない。
教育を変えないといけないときに来ている
*持続可能な社会を作らないと未来はない
「SDGsを教育に!」
注1)
動作の成熟の遅れ 山梨大の中村和彦教授(発育発達学)ら調べ
七つの基本動作で動きの質を幼稚園児で調べたところ、
2007年の年長児は1985年の年少児に近い結果が出た。
最近の調査では、小学3、4年が85年の年長児と同レベルという結果も出たという。
「幼少期にいろんな動きを経験することが減ってしまった」と中村教授は言う。
「子ども同士の外遊びがなくなったことや、幼児期から一つのスポーツをさせる競技志向などが背景にある。
子どもがそうしたわけではなく、いずれも大人の責任。大人が子どもの発達の可能性を奪っている」
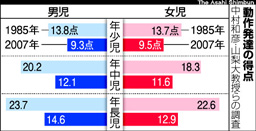

元cotocaのおかあ

-
2015年2月 改田家結成
2018年4月 自宅を改装しこどもたちのお店「こそだて喫茶cotoca」を開業
2021年4月 創ったお店を手離しヨーロッパのマルタ共和国に移住 (言語の獲得)
2022年1月 宮崎県延岡市で「ないもの暮らし」開始 (生きる力の獲得)
自らが考え動き、自らが経験すること。環境を創り、それをこどもと共有すること。生きることを学び、成長して行くこと。
自分に誠実に。こどもに誠実に。
それだけをしている、おかあ・改田 友子です。
※青い地球マークのクリックで
サイトtopに飛びます
最新の投稿
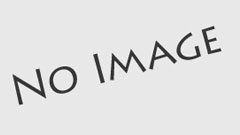 【cotoca 新着情報】2023-09-132021年からの2年半と、閉店の真相と、これから
【cotoca 新着情報】2023-09-132021年からの2年半と、閉店の真相と、これから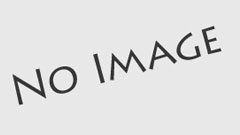 【cotoca 新着情報】2023-06-12みなさまへ重要なお知らせ
【cotoca 新着情報】2023-06-12みなさまへ重要なお知らせ 【cotoca 新着情報】2023-04-07創業おかあがcotocaを手離した理由
【cotoca 新着情報】2023-04-07創業おかあがcotocaを手離した理由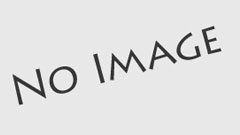 【会員さま限定】日記2022-08-25会員のみなさまへ
【会員さま限定】日記2022-08-25会員のみなさまへ